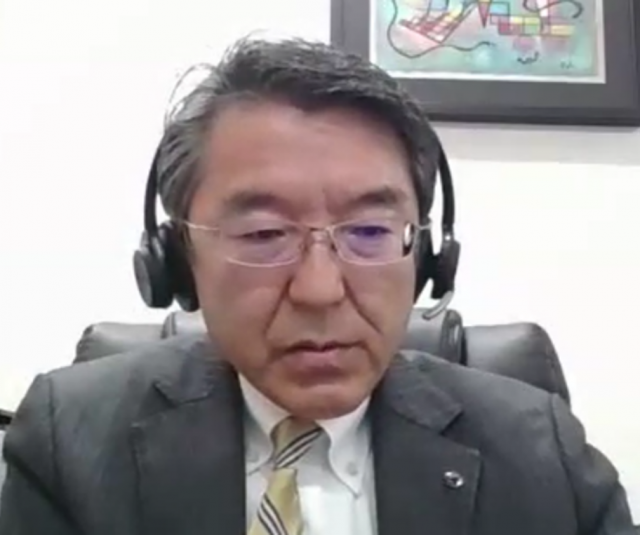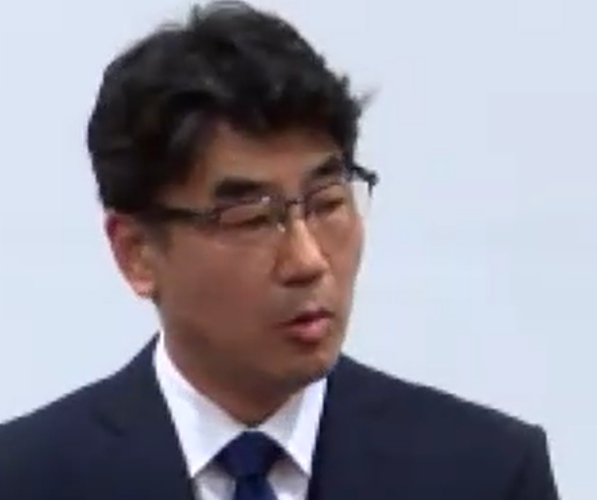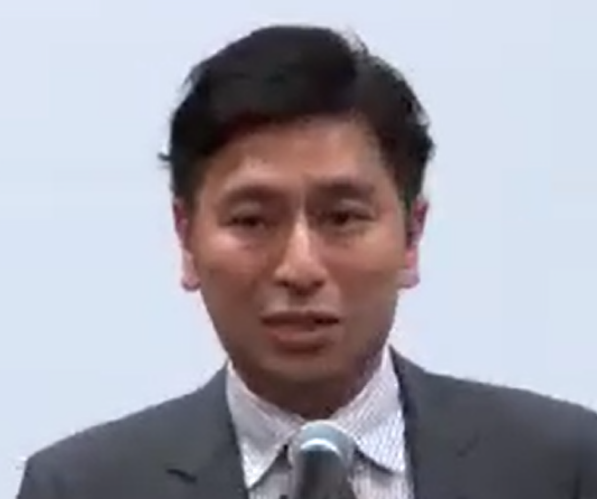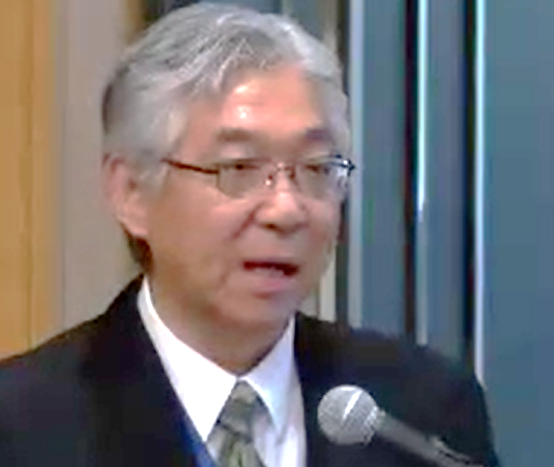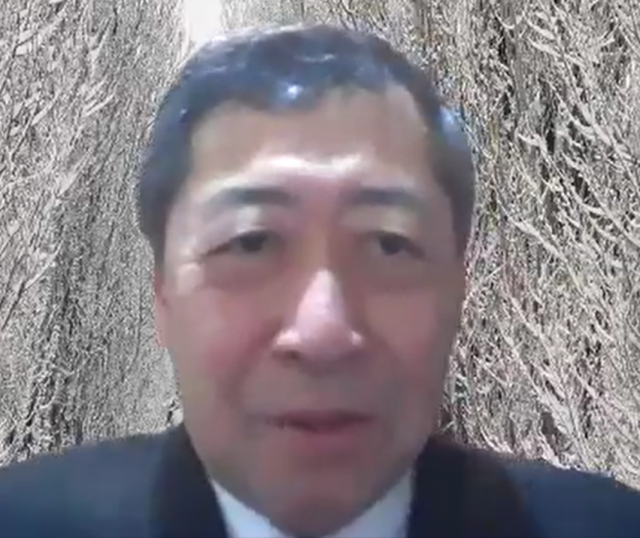お知らせ
news
- ニュース
第4回 Clinical AI アニュアルシンポジウムを開催しました
- 更新日:
2024年2月15日(木)に、北海道大学大学院医学研究院が運営している医療AI開発者養成プログラム(CLAP)に関わる「第4回 Clinical AI アニュアルシンポジウム」を開催しました。本イベントは、北海道大学医学部 臨床講義棟 臨床大講堂及びオンライン(Zoom)配信のハイブリッド形式で行われ、現地から28名、オンラインから216名、計244名の方々にご参加いただき、盛況のうちに終わりました。
Clinical AI アニュアルシンポジウムは、令和2年度に東北大学(主幹校)、北海道大学、岡山大学の三大学が樹立し、文部科学省に採択された「Global×Localな医療課題解決を目指した最先端AI研究開発」人材育成教育拠点-Clinical AI-の成果を発表する場として年に1度開催されています。4年目となる令和5年度は、北海道大学が当番校として開催しました。
Opening Remarksでは、北海道大学の寳金清博総長、文部科学省高等教育局の俵幸嗣医学教育課長、東北大学の張替秀郎副学長、岡山大学の豊岡伸一医学部長、ならびに北海道大学の畠山鎮次医学研究院長より開会のご挨拶および本プログラムにおける今後の抱負について語られました。
過去4年間にわたり、東北大学、北海道大学、および岡山大学は、医療AIの分野での教育と研究に深く取り組み、各大学は独自の強みを生かしながら、医療AIの教育を行ってきました。この集大成として、三大学の教員からその成果が発表されました。東北大学病院AI Labの園部真也助教は、三大学合同の取り組みを紹介し、特に東北大学での成果と今後の方向性に焦点を当てました。事業のコンセプトやプログラムの目的に加え、東北大学がこれまでに達成したマイルストーンと未来への展望を詳細に説明しました。
次いで、岡山大学学術研究院AI人材養成産学協働プロジェクトの谷岡真樹准教授からは、大学院生が中心となって取り組んでいる研究課題に焦点を当てた発表が行われました。また、次年度の事業計画についても触れられました。
三大学の最後に、北海道大学大学院医学研究院画像診断学教室の平田健司准教授が、CLAPを紹介しました。平田准教授は、北海道大学での医療AI研究開発の基盤と、CLAPが提供する学生が利用可能な教材、ハードウェアリソースに関する情報、そしてHU VISION 2030 (ExcellenceとExtension)と関連させてCLAPの理念について話しました。また、CLAPが主催する行事や令和6年度の事業計画についても紹介しました。
それぞれの発表からは、大学の特色を活かしながら、日々熱心に行われている医療AI教育について深い理解を得ることができました。また、社会人の受講者数が飛躍的に増加していること等から示される様に、社会における医療AI教育のニーズが高まっており、この背景を踏まえ、各大学は医療AI教育にさらに注力し、この重要な分野でのリーダーシップを確立するための決意を新たにしました。
「大学院生の報告」セッションでは、東北大学、岡山大学、および北海道大学の大学院生が、それぞれの大学での活動とAI研究の進捗を報告しました。このセッションでは、東北大学大学院医学系研究科の神経外科学分野 永井新先生、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科の血液・腫瘍・呼吸器内科学 高田健二先生、そして北海道大学大学院医学研究院の画像診断学教室 西岡典子先生が、各自の専門分野での研究成果とAI技術の応用について熱心に語りました。
発表後の質疑応答セッションでは、座長である北海道大学大学院医学研究院画像診断学教室 工藤與亮教授のもと、活発な議論が展開されました。ここで行われたディスカッションでは、医療AI教育における重要なポイントや、プログラムを通じて得られた知見、さらには学生や研究者が直面する課題や機会について、深く掘り下げられました。
シンポジウムの後半には、「社会変革における医療情報・AIの役割」と題した特別講演が、北海道大学大学院保健科学研究院健康科学分野 小笠原克彦教授によって行われました。この講演では、現代社会における医療情報技術とAIの革新的な役割について、深い洞察が共有されました。小笠原教授は、日本全国および北海道における医療の現状と、これらの技術がどのようにして将来の医療サービスの向上に貢献できるかを語りました。また、これらの技術を社会に広く実装するための前提条件として、適切な法整備や倫理的枠組みの構築の重要性を強調されました。このセッションは、技術的進歩がいかにして医療分野における大きな社会変革を促進するかを理解するための貴重な機会を提供し、参加者に深い印象を残しました。
続いて、メディカルAI人材養成産学協働拠点から名古屋大学大学院、木村宏研究科長よりご挨拶および拠点紹介がなされました。木村研究科長は、ご挨拶と共に、拠点の活用概要、また、医療AI分野での革新的な研究と教育への貢献について紹介されました。
本シンポジウムは、北海道大学病院 渥美達也病院長による締めくくりの言葉で幕を閉じました。渥美病院長は、シンポジウムを通じて展開された議論、発表された研究成果、そして共有された知見に感謝の意を表しました。
医療AI開発者養成プログラムでは、医療AIというテーマは、現代社会において極めて重要であり、今後の学術的な発展だけでなく、社会全体に大きな影響を与えるものと考えており、このシンポジウムを契機に、関係者の医療AIへの理解が深まり、さらにその裾野が広がっていくことを強く望んでいます。
また、医療AI開発者養成プログラムでは、今後も、人脈形成、国際的視野の形成、共同研究の機会や将来のビジョン、キャリアパスの形成に繋がるようなイベントを積極的に開催していきます。学部生、大学院生、教職員の皆様の積極的なご参加をお待ちしております。